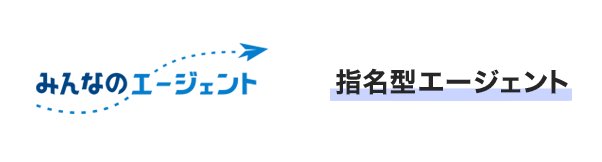【初心者向け】コンピテンシーとは?意味や代表的な例を解説
目次
コンピテンシーとは
コンピテンシーの定義
コンピテンシーとは「高いパフォーマンスを示す従業員の行動特性」のことを指します。英語の”Competency”は「能力」や「適格性」と訳されますが、人事の文脈において前述のような意味で用いられます。
高い実績や優れた成績を収めている目に見えて優秀な従業員に共通する、能力や技能、性質、考え方、行動などを分析し、高いパフォーマンスを上げられる理由を理解できれば、人事や採用、能力開発や人材育成にも有効活用できるため、今、コンピテンシーは多くの企業から注目を集めています。
企業がコンピテンシーを活用する場合、コンピテンシーの評価モデルを設定しなければなりません。モデルの策定は自社で高いパフォーマンスを上げる社員にインタビューして独自に評価項目を模索する方法のほかに、既存のモデルを利用する方法もあります。
コンピテンシーの歴史と背景
元々、心理学用語として生まれたコンピテンシーがビジネスの世界で知られるようになったのは、1970年代に行われたハーバード大学のマクレランド教授による調査研究および論文がきっかけだったと言われています。
マクレランド教授はアメリカ国務省から外交官の能力に関する調査として、外交官を採用する際のテスト結果と合格後の実績の相関性について調べました。調査と分析の結果、マクレランド教授は優秀な成績を上げている外交官と、そこまでではない外交官の間に下記の事実が成り立つことを突き止めました。
- 学歴やIQは、業績の高さとさほど相関関係はない
- 高い業績を上げている職員には共通する行動特性がある
この調査結果が公表されたことで、成果を上げる行動特性がモデル化され、アメリカ国内でコンピテンシーを評価に組み込む企業が増えていきました。
日本でも成果主義が注目を集めるとともに1990年代後半からコンピテンシーが注目を集めはじめ、コンサルティング会社や研究者などが実務的なモデルを提唱するようになりました。また、近年では労働生産性が重視されるようになり、改めてコンピテンシーに注目が集まってきています。
コンピテンシーの代表的な項目例
コンピテンシーの代表的なモデルに「Spencer & Spencer」のモデルがあります。Spencer & Spencerはコンピテンシーモデルの要素を「コンピテンシー・ディクショナリー」と呼び、インパクト・対人影響力及び、以下の6領域20項目を掲げました。
| コンピテンシー | コンピテンシーの定義 |
|---|---|
| 達成・行動 |
|
| 援助・対人支援 |
|
| インパクト・対人影響力 |
|
| 管理領域 |
|
| 知的領域 |
|
| 個人の効果性 |
|
こうした古くから用いられてきたコンピテンシーモデルの他にも、多くの企業がそれぞれに合った独自の評価項目を設定しています。以下はあくまで一例として列記します。
| 傾聴力 | 読解力 | 記述力 | 提案力 |
| 議論力 | 課題発見 | 課題分析 | 論理的思考 |
| 計画実行 | 検証 | 学習意欲 | 成長意欲 |
| 応用力 | バランス力 | 役割認識 | 主体性 |
| 協働 | 率先力 | 発想する力 | 推論する力 |
| 感動する力 | 探求する意欲 | 倫理 | 目標設定 |
| 計画力 | 進捗管理 | スケジュール管理 | 自確力 |
| 協創力 | 共感力 | 達成志向 | ストレスコントロール |
| 誠実な対応 | プレゼン能力 | プロフィット | 人的ネットワーク |
| 戦略策定 | 変革力 | 説得力 | 解決案の提示 |
コンピテンシーと類語の違い
コア・コンピタンスとの違い
コア・コンピタンスとは「企業の競争力の源泉となる中核技術や能力」のことを指す言葉です。
顧客に価値をもたらす自社ならではの能力や、競合企業に真似されにくい独自技術などが、コア・コンピタンスに該当します。コンピテンシー同様、コンピタンス (Competence) は「能力」と翻訳される英単語であり、直訳すれば中核 (Core) 能力 (Competence) です。
コンピテンシーが従業員などの人を対象としたパフォーマンスについての文脈で使われる用語なのに対して、コア・コンピタンスは企業や組織を対象とした文脈で用いられる点が大きく異なります。
なお、コア・コンピタンスの類語に「ケイパビリティ」があります。コア・コンピタンスが特定の能力や技術を切り口としているのに対し、ケイパビリティは組織的な能力を切り口とした競合優位性について語る際に用いられる用語です。このケイパビリティも企業や組織についての用語であるため、コンピテンシーとは対象が異なります。
スキルとの違い
スキル (Skill) は直訳すれば「技術」「技能」であり、ビジネスの文脈では従業員個人が有する何らかの技能がスキルに該当します。
スキルという単語の特徴はその広範な用いられ方にあります。例えば ”ビジネススキル” という単語にはかなり広い能力が含められます。
課題解決能力や計画能力などコンピテンシーの範囲に含まれる能力もビジネススキルの範疇ですし、広義にはビジネスマナーなどの基礎的なものもビジネススキルに含まれるでしょう。
また、特定の分野に関する専門技術や専門知識などもスキルの一部と言えます。ITスキル、マネジメントスキルなどがこれらに分類されます。さらに、どのような組織に属していても必ず役に立つポータブルスキルなどの分類も存在します。
このように広範な能力を包含するスキルの中でも、高いパフォーマンスを示す従業員が共通して持っているスキルがコンピテンシーだと言えます。言い換えれば、スキルという用語の中にはパフォーマンスとはあまり関係がない能力も含まれていると言えます。
なお、スキルの類語に「アビリティ」があります。アビリティもスキル同様に広範な能力を含む単語ですが、スキルほど高度で確かな能力を指さず、「できること」に近い意味合いで用いられることが多い単語です。
コンピテンシーの活用シーン
人事評価に活用
人事評価はコンピテンシーが最も活用されている分野のひとつです。高いパフォーマンスを上げる従業員に共通した行動や能力が定義されていれば、明瞭で公平な人事評価をしやすくなります。
人事評価にコンピテンシーを本格活用しようとした場合、脈々と利用されてきたコンピテンシーのモデルを踏まえつつ、自社のハイパフォーマーに対してヒアリングを行い、評価項目を選定し、各項目についてレベルを設定し、独自のコンピテンシーモデルを設計することになります。
こうしたコンピテンシーモデルに従い、各従業員が成果を上げるための能力を持ち合わせているか、どれだけ考えや行動特性がコンピテンシーに沿っているかを見極めます。
正しくコンピテンシーモデルが設計されていれば、足元の成果や結果だけではなく、成果に至るプロセスを評価できるようになるため、(論理的には)公平で効果的な評価が可能になります。
ただし、どれだけ完璧に見えるコンピテンシーのモデルであっても、人が作ったものである以上は完全ではありません。過信しすぎず、上手に活用することを心がけると良いでしょう。
採用に活用
コンピテンシーは採用にも活用できます。社内で成果を出したハイパフォーマーの行動特性を分析し、同じ共通点を持った人材を採用すれば、入社後の活躍も期待できるでしょう。
既にコンピテンシーモデルを設計して人事評価などに活用している企業であれば、採用にコンピテンシーモデルを活用するのは難しくありません。採用試験で応募者が語った内容からコンピテンシーの評価項目を満たす能力があるかを判断し、自社で活躍できる人材かを見極めることが可能です。
人材育成に活用
コンピテンシーは人材育成にも活用ができます。高いパフォーマンスを示す従業員の行動特性をナレッジとして共有すれば、多くの従業員にとって何を心がけて働けば良いかを判断する指標となります。
コンピテンシーに沿った行動や考え方について学ぶ社内研修などを通して浸透を促したり、人事評価の評価項目になることを周知したり、コンピテンシーに沿った成長目標を設定させたりすることで、ハイパフォーマーとなる人材を育成していくことが可能です。
こうした明確な方向性と目標設定が示されることは、従業員のモチベーションのアップにもつながるため、コンピテンシーを共有・公表していくことは人材育成においても有効な施策だと言えます。
コンピテンシーを評価に活用するメリット・デメリット
メリット
コンピテンシーの主なメリットは以下の3点です。
- 従業員のパフォーマンスが高まる
- 効果的で公平な人事評価につながる
- パフォーマンスの高い人材の採用につながる
前章で説明したように、従業員にコンピテンシーを共有することで従業員全体の生産性向上を目指した人材育成が可能になる点は、コンピテンシーモデルを作る大きな目的であり、メリットだと言えます。
また、明確な評価項目とレベルを打ち出すことは、人事評価に対して従業員が納得感を得やすくなるほか、従業員のモチベーション向上にもつながります。
さらに、設計したコンピテンシーのモデルを採用活動でも活用することで、高いパフォーマンスを示すことが期待される人材の採用を後押しすることも可能です。なお、採用へのコンピテンシーの活用は、新卒採用・中途採用のどちらに対しても有効です。
デメリット
コンピテンシーのデメリットは主に以下の3点です。
- コンピテンシーモデルの策定に時間と労力がかかる
- 環境に合わせた見直しが必要
- 必ずしも正しい成果につながる保証がない
コンピテンシーには「Spencer & Spencer」などの代表的なモデルは存在するものの、ほとんどの企業ではこれをそのまま導入しても劇的な成果を上げることは困難でしょう。実戦レベルでコンピテンシーを活用するためには、独自のコンピテンシーモデルを作り上げる必要があると言えます。
そのためには、異なる部門や異なる職種で高いパフォーマンスを上げる従業員にヒアリングを行う必要があり、膨大な時間と労力を要します。
また、コンピテンシーのモデルを策定して人事や採用などに活かし始めた後も、評価項目などについて定期的に見直すことが必要です。ビジネス環境は日々変化しているため、その時代に合った評価基準を模索し続けなければなりません。こうした見直しにも時間やコストがかかる点も見逃せないデメリットです。
さらに、こうして策定したコンピテンシーの評価モデルも、人が作ったものである以上は完全なものである保証はどこにもありません。思わぬ見落としや例外などが必ず発生するため、万能のツールとはなり得ないことも忘れてはなりません。
コンピテンシー評価を企業が導入する手順
手順① ハイパフォーマーにヒアリングする
コンピテンシーの評価モデルを導入する際、まず企業が行うのは高いパフォーマンスを示している従業員へのヒアリングです。
ヒアリングの目的はハイパフォーマーの行動特性を把握することですので、さまざまな角度からインタビューをし、他の従業員との差異を見つけ出します。場合によっては、ヒアリングだけでなくハイパフォーマーが実際に仕事する様子を観察するケースもあります。
また、ヒアリングは部署や職種ごとに複数のハイパフォーマーに行うと良いでしょう。複数人を深く観察することで、共通する行動特性が見つかることもあります。さらには、ハイパフォーマー以外の同僚にインタビューをして、ハイパフォーマーについて第三者の視点から見えることを語ってもらうことも有用です。ハイパフォーマー自身が気づいていない特性が見えてくる場合もあります。
手順② 評価するコンピテンシーを選定する
ハイパフォーマーにヒアリングを行い、行動特性のサンプルを集めた後は評価するコンピテンシーを選定します。すべての行動特性を評価項目として取り入れようとしてしまうと、評価軸がぶれる、運用に負担がかかるなどデメリットが多くなってしまいます。そのため自社の企業理念やビジョンに沿って、評価項目の取捨選択をすると良いでしょう。
場合によっては、従業員の育成に適した項目を積極的に残す、人事評価に利用しやすい項目のみ残すなど、利用目的に応じて残す評価項目を選定しても良いかもしれませんし、特に成果への影響力が大きいと思われる評価項目のみ残すのも手です。
手順③ 各項目をレベル分けする
コンピテンシーのモデル策定の最後のステップはレベル分けです。
手順②で選定した評価項目それぞれについて3段階~5段階程度でレベル分けをし、それぞれのレベルの達成基準を明確にします。例えば「チームワーク」というコンピテンシーの評価項目を設定した場合、以下のような基準を設けます。
| レベル | 達成基準 |
|---|---|
| レベル0 | チームと協力できない、自己中心的な行動が目立つ |
| レベル1 | チームで動いてはいるが、能動的に行動しない |
| レベル2 | チームでの自身の役割を理解し、目標達成のために協力できる |
| レベル3 | チームの目標達成のために積極的に行動し、チームの一員として欠かせない役割を果たしている |
こうしたコンピテンシーのレベル分けについては、中央大学がまとめる「コンピテンシー定義一覧」に詳しく記載されているので、一読してみても良いでしょう。
コンピテンシーのレベル分けは、評価基準として利用するためにも有用ですが、従業員が次のステップに進むために具体的にどのような行動を取るべきかが見えるようになるため、行動の改善につながることにも価値があります。
まとめ
多くの人は、高い生産性を示す従業員に共通した考え方や行動があることを経験的に理解していることでしょう。しかし、こうした行動特性を体系的に取りまとめ、人事や人材育成、採用などに積極活用しようとする企業はまだまだ少ないと言えます。コンピテンシーの概念はまだまだ日本では浸透しきっているとは言えません。
ハイパフォーマーの行動特性を理解することは、企業にとっても従業員にとっても成長のきっかけとなり得ます。多くの企業でコンピテンシーが有効活用され、生産性の高いビジネスパーソンが一人でも増えていくことを願っています。
- この記事をシェア -

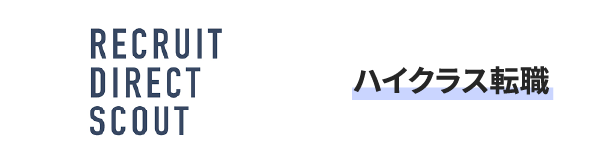
 アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティング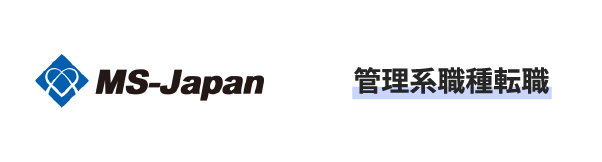 MS-Japan
MS-Japan
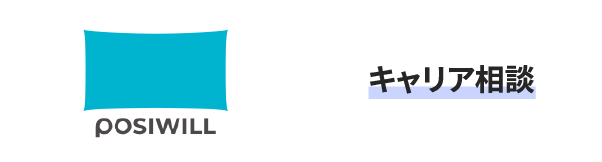 ポジウィル
ポジウィル